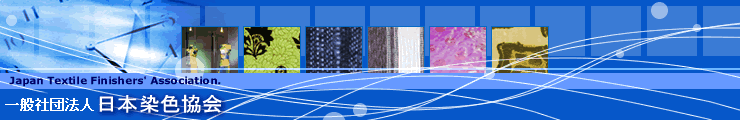化学知識の必要性を感じた
それまで染色といえば、染料を水に溶かし、それを釜の中へ糸か布を入れる、煮きこめば染まるという単純な発想でした。そのため、各繊維産地の染色業者で大量の不上り事件を起こし、社会的に非難された史実があります。
明治16年〜17年にかけて八王子では輸入合成染料が使われるようになりましたが、合成染料を使う知識と経験がなかったことで、一度、洗濯するとたちまち変色した。このため八王子織物の信用は著しく低下しました。
当時、染色の本場といわれた京都でも同じ事件が発生しています。明治の初め、京都の染色業はすでに社会的分業形態が確立していました。茶染業を中心にして紫染め、紅染め、藍染めといった無地染めの技術集団、紺染め、友禅染めの技術が日本で最高の染色技術を確立していました。その技術を打ち砕く第一歩になったのが1862年です。
京都の紫染め業者の井筒屋忠助が欧州製の化学染料、すなわち合成染料を手に入れ、染色を試みたからです。
明治維新を契機に合成染料の鮮明さに注目した京都の染色業者は次々と合成染料を輸入し使用するようになりました。
しかし、八王子の染色業者と同じように京都の染色業者も従来の植物染料の知識しか持ち合わせていなかったことで、色落ち、日光堅牢度低下の欠点が出て、西陣織物や京染めの名声に傷がつきました。
この打開策として京都府は明治6年(1873年)に京都舎密局の局員、京都の染色工を大阪に駐在していた外人キンドレのもとへ派遣し、英国の黒染法を研修させました。
ドイツ人ワグネルの染色技術教育場になっていた京都舎密局でも明治8年(1875年)にオーストリア万国博覧会を視察するため、担当者を派遣、新しい欧州技術の進歩を肌で感じさせ、更に欧州各地で染色技術を実習させました。
近代染色と伝統的な染色の分離はその頃から本格的に始まったといえるでしょう。
平成時代の一般の消費者の方々の中で、染色を天然染料で染めるがごとく、単純に感じている人があります。しかしそれは全く誤りであることを、以上の歴史的経過で、理解していただけるでしょう。