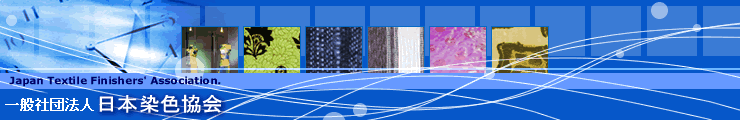輸出産業の基礎になったクロールカルキ使用
明治時代は近代化日本の出発点になった。その原動力になったのは綿布の輸出拡大である。
この拡大は後の大正、昭和時代で大きく花が開くわけだが、その基礎がつくられたのは明治16年〜17年(1883年〜1884年)頃である。
それまでの木綿、麻の漂白は和晒法と称される、単純に日光で晒すだけの天日晒という方法で行われた。その内容は灰汁で木綿を煮て、それを引き出して河原に広げ太陽の光で晒し、布が乾燥すると、それに打ち水をして更に太陽で晒すという方法だった。雪の上で晒す方法も行われていた。
河原に晒すと強い太陽の光で晒し上がりが強くなった。それに対して、芝生の上で晒すとゆるやかなソフトな晒し上がりになったと記録されている。
以上のような和晒法だと晒し上がり量が限定される欠点があった。量産を可能にするために、欧州ではクロールカルキの使用が一般的になっていた。クロールカルキとは晒し粉(次亜塩素酸カルシウム)のことである。明治16年頃から晒し粉が欧州から輸入されるに及んで、その漂白法は舎密晒、又は洋晒しと称された。
晒し粉の使用で木綿を漂白する大工場が建設され、綿ネルを中心に大量漂白されるようになった。そして機械捺染工場の発展を促した。
晒し粉利用の漂白法について、大和木綿商仲間の<木綿糸の晒し方>で次のように紹介されている。
その内容原文はわかりにくい個所があるので、それを具体的に紹介した京都近代染織技術発達史から引用すると下記の通りである。
「木綿糸の4分〜5分−1貫目に付、40〜50目(匁)の洗いソーダを釜の湯の中にて溶かし、又はボウメ1度〜2度の木灰汁にて3時〜4時間、煮た後に、充分に水にて洗い干すべし。
- ボウメ1度半から2度のクロールカルキ(晒し粉)水に、前のごとく煮たる木綿糸を漬ければ、次第に白色となる。絞り出して第2の手順を為すべし。クロールカルキすなわち晒し水の製し方は、クロールカルキを磁壺に入れ、水少量を注ぎ入れ、粒なきように砕き、尚、水を多分に注ぎ入れ、かきまぜて、壺を密封して放置すべし。石灰分は壺の底に沈み、上水清く澄む。尚、之を濾して他の壺に入れ、密封して貯うべし。是れ晒し水なり。
- 中和、脱塩素処理をして水に硫酸を交ぜて、大概ボウメの半度〜1度となりたるものに、晒し水より絞り出せる木綿糸を漬け入れ、およそ30分〜1時間して絞り出して、充分に水にて洗うこと。
和晒しは太陽任せだった。
和晒法では雨や曇りの日には晒し作業が出来ない。それに対して洋晒しは天候に左右されず作業が出来たことである。
伝統工芸と近代染色の違いは後者の場合、天候に左右されずに労働を継続出来るメリットがあった。
しかし労働生産性を高めるためには、(1)人力による生産性では限度(生産量)があるので、これを打破する必要性があった。
もう一つは、(2)特定の人物しか伝承されない染色技法を、多くの作業者たちが容易に使えるようにするため、技術を公開することであった。
以上(1)と(2)を具体的に説明すると、(1)の人力依存を打破し労働生産性の向上のために機械化した。この使用効果は大きかった。絹の精練作業を向上させるため、石鹸精練への転換が明治末から本格化した。その結果、日本で石鹸の製造が本格的になった。明治中期にボイラの導入で絹の精練釜として蒸気加熱による加熱方式を実施、間接蒸気加熱の二重釜や、循環式精練槽の発展につながった。ボイラ利用は明治末から日本の染色工場で増え、ボイラによる熱源利用で工場の生産体制は高能率化した。洋式の近代工場と従来の工場を区別するため、前者をボイラ組、後者をかまど組と称された。
次回で明治時代において、(2)の技術移動をどのように円滑に促進したか、その背景について述べてみたい。