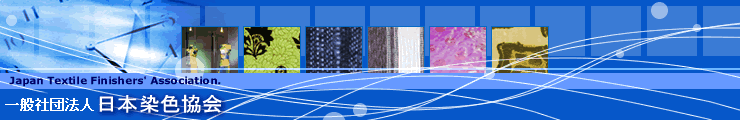国内技術移動を促し、7項目の重要性を説いた西田博太郎博士
明治から大正、昭和にかけて、日本の染色、化学教育に貢献した西田博太郎工学博士は明治以後の近代化の柱になった7項目について、注目すべきことを述べている。
「化学工芸」(大正6年)に西田博士が寄稿した内容で次のように素晴らしいことを書いている。
「産業発展には7条件がある。産業といえば漠然とした表現になるので、水産、林業、農業、鉱山業も製造工業に入る。それら産業を一括して論ずるわけにはいかないが、しかし、共通した原則的な要件がある。7つの原則を実行してこそ、産業は発達する。
- 経済的な頭脳を有する技術者を養成しなければならない。
- 産業思想の普及を図ること。
- 小規模の産業に対する金融制度の完備が必要。
- ある程度までの保護対策が必要。
- 交通運搬の発達が必要。
- 機械工業の発達を促す。
- 原料製造的な化学工業の独立が必要。
以上の7条件のどれが一番大切か選ぶことは出来ない。強いていえば技術者の養成こそ、産業独立の根本となる。
ロシア(当時の帝政ロシア)のようになってはいけない。ロシアは自国の技術者の養成に遅れがあり、ドイツ、フランスから技術者を招き、彼らから学び取る気構えに欠けていた。大戦乱がなくても、一旦、ドイツ、フランスとの国交が断たれると、ロシアはたちまちドイツ、フランスの技術者は母国へ帰ってしまう。そうなると技術者不足となり、作業は停止しなければならない。又は作業能率は低下する。ロシアが各種の工業分野の技術者を遠く米国にまで求める現状を目撃すると国家のため、何が重要か認識させられる」と述べている。
西田博太郎博士は付け焼き刃の技術水準では、産業は絶対に発展しないと指摘すると共に、理工系の教育の場合、学校教育の充実を土台にして、技術者間の技術移動(テクノロジートランスファー)の必要性を説き、それを実行している。偉大な人だった。
多くの日本人技術留学生たちは、欧州で学んだ新知識を個人だけの知識にとどめず、多くの人々に技術移動した史実が多い。染色技術者もその例外でなかった。
(つづく)